2024年に新NISAが始まりました。
投資初心者の人は様々な情報が行き交う中で、何から始めれば良いのか悩んでしまいますよね。
投資を始めるのに何が必要か、どれを選べば良いのか知りたいところです。
この記事はPRを含みます。

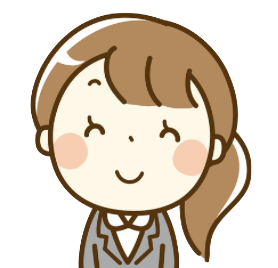
スポンサーリンク
新NISAで初心者におすすめの投資は?
新NISAを始めたばかりの初心者にはどの投資方法を行えば良いか悩むこともあるかと思います。
初心者の人は投資の知識を得るのに時間がかかることや値動きに一喜一憂したり、購入タイミングを間違え損失を出してしまうなど失敗をする可能性があります。
初心者にとって失敗のリスクが少なく、投資を始めやすい高配当株投資、株主優待投資、投資信託について解説していきます。
高配当株投資について
高配当株投資は株価に対する配当金の利回りが高い株式のことを言います。
はっきりとした定義はありませんが、一般的には配当利回りが3~4%以上の商品が高配当株と言われています。
例えば、1株2,000円で年間配当金額100円の場合、100÷2,000×100=5で配当利回りは5%になります。
利回りが高い高配当株投資をすることで、高い配当金を得ることが可能です。
通常だと配当金の受取には20.315%の税金がかかりますが、新NISAで配当金の受取が非課税になります。
スポンサーリンク
高配当株投資のメリット・デメリット
| 〇メリット |
|
| ×デメリット |
|
高配当株投資のメリット
・安定した配当収入を得られる
日本株は半年ごと、米国株は3か月ごとに配当金が支払われることが多く、配当利回りも高いので安定した収入を得られます。
・値動きが安定している
高配当株は配当目的で株を購入する人が多く、売却されにくいので他の株と比べて値動きが少ない傾向があります。
・再投資で資産を増やせる
受け取った配当金を再投資することで、さらに配当金を得るといった福利効果を得ることが可能です。
高配当株のデメリット
・減配・無配リスクがある
配当金は企業の業績により決められているので、悪化すると配当金が減配したり無配になる可能性があります。
・売却益を狙うのが難しい
高配当株を発行する企業は、一般に業績が安定しており株価の変動も比較的穏やかであることが多いです。したがって、株価上昇が見込みづらく売却益を狙うのが難しい傾向にあります。
・値下がりのリスクがある
上でも述べたように高配当株を発行する企業は業績が安定している傾向にあるので、徐々に株価が値下がりし、最終的に株を売却した時に損失が出る可能性があります。
スポンサーリンク
株主優待狙いの投資について
株主優待は株を購入した企業から優待品がもらえる制度です。
自社商品やサービス、商品券などの提供がありおよそ1000以上の企業で株主優待が行われています。
ただ、株主優待を受けるためには株を購入した企業が定めている権利確定日に株主名簿にの記載されていなければなりません。
したがって、権利確定日の2営業日前である権利付最終日までに株を購入する必要があります。
さらに各企業ごとに株主優待をもらうのに必要な株数が決まっているので事前に確認しましょう。
株主優待投資のメリット・デメリット
| 〇メリット |
|
| ×デメリット |
|
株主優待投資のメリット
・株主優待品がもらえる
実際に利用しているサービスの割引を受けられたり、興味がある商品が手に入るなどお得な気分を味わえます。
・株価の下落に強い
株主優待株は優待品を目的としている人が多く、株価が下落しても簡単に株を手放すことがありませんので株価の下支えになります。
さらに株価が下がることで追加購入や株数を増やし優待内容を良くするチャンスにもなります。
・長期保有しやすい
株主優待を目的として投資をすれば株価を気にすることなく保有できます。
また、株主優待株を長期保有することで優待品内容がアップグレードすることもあります。
スポンサーリンク
株主優待投資のデメリット
・優待品の廃止や改悪の可能性がある
株を投資する企業が業績の悪化などによる理由で優待品を廃止、改悪する可能性があります。
・株価の下落で損失リスクが高まる
優待品の廃止や改悪で、株主が保有株を手放すことで株価が急落するリスクが高まります。
株価の下落で損失が出る可能性があります。
人気の株主優待をランキング形式で紹介している下記の記事も参考にしてみてくださいね。
株主優待とは、企業が自社の株を保有している株主に自社製品や、QUOカードなど魅力的な優待品をプレゼントしてくれる日本特有の制度です。 株主優待をもらえる上場企業はたくさんあります。 元プロ棋士であり投資家の桐谷さん(桐谷広人さん)に影響[…]
投資信託について
投資信託は投資信託運用会社で作られており、証券会社や銀行などの販売会社を通じて投資家から資金を集めます。
集められた資金は管理・保管している信託銀行に渡り、運用会社がどこにどのくらい投資するのかを信託銀行に指示し、株式や債券の売買を行います。
運用成果が出た場合、信託銀行から販売会社に分配金・償還金が渡され投資家たちに利益を還元する仕組みです。
投資信託は販売・運用・保管などそれぞれの機関で役割を担うことで成り立つ金融商品です。
投資信託では値段のことを基準価額といい、取引単位のことを1口と呼びます。
投資信託のメリット・デメリット
| 〇メリット |
|
| ×デメリット |
|
投資信託のメリット
・少額から購入できる
株式投資の場合、まとまった資金が必要になることもありますが、投資信託は1万円程度の少額から始められます。
中には100円から投資できるプランもあり初心者でも手軽に始められるでしょう。
・専門家が運用してくれる
初心者だと知識を深めたり投資のタイミングを覚えるのに時間を要します。
しかし投資信託は運用の専門家がいるので、投資家に代わり運用してくれます。
・分散投資ができる
投資信託は複数の投資家から集めた資金を元に運用。
複数の国内外の株式や債券などを組み入れるので分散投資することができます。
投資信託のデメリット
・元本が保証されるわけではない
投資信託は預貯金とは違い元本保証がされない金融商品です。
投資信託の基準価額も市場の変動に少なからず影響しますので運用方針などによっては損失が出る可能性もあります。
・短期間での利益が出にくい
投資信託は長期運用を前提とした商品です。
分散投資の効果で価格変動の影響を低く抑える効果がありますが、大幅な値上がりもしにくいため短期間での利益は出にくいでしょう。
・商品が多すぎて選択が難しい
日本の投資信託は5,900本以上あります。
運用方針などを見比べてみても商品が多すぎるのでどれを選べば良いか迷ってしまうと思います。
スポンサーリンク
投資で失敗しないための初心者の3つの心得
投資を始めたばかりの初心者の人は、失敗したらどうしようと不安な気持ちもあるかと思います。
投資で失敗しないための3つの心得をご紹介していきます。
投資の目的や目標を定める
投資を始める理由や目標金額を定めることで、投資についての具体的な計画を立てることができます。
目標を達成するためにどうすれば良いか明らかになり、外部から入る情報などに影響されずに運用できます。
資金に余裕を持って運用する
手元にある資金を全部投資すると急にお金が必要になった時に積立を崩すことになり、複利効果を実感することなく成果が思うように出ないことにもなります。
日常生活に影響が出ない範囲で運用をしましょう。
リスクがあることを心得ておく
投資は元本保証がない商品なので、どの種類でもリスクがゼロというわけではありません。メリットばかりに目がいくと失敗する可能性もあります。必ずリスクがあるということを心得て無理のない運用を心掛けましょう。
スポンサーリンク
新NISAで初心者におすすめの投資についてのよくある質問
新NISAで初心者におすすめの投資についてのよくある質問を集めてみました。
新NISAで1ヶ月にいくらまで投資できますか?
つみたて投資枠での月間積立上限は10万円です。年間120万円の上限額を一括投資することも可能です。
また、成長投資枠での月間上限は積立額で20万円、年間240万円の上限額を一括投資することも可能です。
新NISAで20代は毎月いくら貯めればいいですか?
20代の方が毎月積み立てるとしたら、余裕のある資金で始めると良いので毎月5,000円や1万円を投資すると良いと思います。
積立投資は時間を味方につけ、複利の力で稼いでいくので淡々と決めた額を毎月積み立てていくものです。
例えば5,000円を年利4%で30年積み立てると約3,470万円(元本1,800万円)になり、1万円を年利4%で30年積み立てると約6,940万円(元本3,600万円)になります。
つみたてNISAの暴落リスクは?
NISAで積立中に株価が暴落した場合、焦って下がったタイミングで売ってしまう狼狽売りをする人は元本割れのリスクがあります。
長い目で見ると、暴落した株がそのまま低い水準でとどまることはありません。むしろ下がったタイミングは沢山の口数を買えると前向きに捉え、淡々と積立を続けることが大事です。数年、数十年後には暴落があったおかげで資産が増えた、と喜ばしい結果が訪れる可能性が高いです。

